療育施設(児童発達支援・放課後等デイサービス)を利用するにあたり、必ず必要なのが通所受給証です。
その申請にあたり、これまた必要だったのが、医師の診断書(意見書)とサービス利用計画書(セルフプラン)でした。
今回は、この1つ「サービス利用計画書(セルフプラン)」を書き上げた時のコツをまとめます!
医師の診断書(意見書)は並行してゲットしておく
※私が苦労の末、医師の診断書を入手した経緯は、別記事(上記リンク)の通りです。
療育などに通うために通所受給証の申請/取得をする時は、複数の書類をまとめて提出しました。
この”まとめて提出”に向けて必要書類を揃えていくわけですが、一番時間(労力)がいるのは…今回書き上げるセルフプラン。
セルフプランの準備と並行して、医師の診断書(意見書)はゲットしておくとスムーズです。
最短!?申請からわずか2週間で通所受給者証が発行された
これから療育(児童発達支援)を始めようという私が、なぜ偉そうに記入事例をまとめようと思ったのか?
それは、申請から発行までわずか2週間で、通所受給者証が自宅に届いたからです!
誰にも相談できず一人で書き上げた「サービス利用計画書(セルフプラン)」(以下『セルフプラン』)ですが申請後なんと、この地域では”最短”と言われる2週間で、通所受給者証が発行されました。
この時のセルフプランをご紹介しつつ、記入例を分析したいと思います。
セルフプランとは?

療育施設・児童発達支援・放課後等デイサービスなどに通所するためには、受給者証が必要です。
この通所受給者証を発行してもらうために、「サービス利用計画書」を作成して提出(申請)しなければなりません。
「サービス利用計画書」の作成・申請までを保護者自身で実施するのがセルフプランです。
セルフプランは少数派だった
私が息子の療育を始めようと思った当時は、「サービス利用計画書」の準備にあたってセルフプランを選ぶなんて珍しく少数派でした。
「サービス利用計画書」は、相談所や指定施設で記入を申し込むのが普通、と言われる風潮。
「サービス利用計画書を自分で書く」という時点で、挑戦せずに諦める保護者が多数派でした。
ゆえに通所受給者証は(地域・自治体にもよるけど)、発行までに1ヶ月~2ヶ月かかると言われていたのです。
セルフプランのメリットとデメリット
メリット
セルフプランのメリットは、何と言っても通所受給者証が発行されるまでの早さだと思います。
役所に相談した時、発行までに1ヶ月~2ヶ月かかるとも言われた通所受給者証が、「もしもセルフプランで申請するなら、早ければ2週間で発行される」と言われました。
デメリット
一方で、セルフプランのデメリットは、文字通り自分で書かなければならないこと。
情報の整理や記入の大変さだけでなく、子供の障害や生き難さについて事実を受け止めながら、我が子の課題を冷静に整理しなければならない精神的な負担もあります。
そこに分からない記入方法。どの項目に何を書く?どんな文章がいい?書き方が有利/不利/却下とかに繋がる?…分からないことだらけでした。
他人に任せる方が大変?セルフプランの方が楽かも?
とうわけで、セルフプラン最大の関門は「自分で記入する」ことですが、逆に考えると自分一人で完結できるという手軽さも持ち合わせています。
これは私がセルフプランに決めた大きな理由でもありますが、これから療育に通う子を育てているということは、子供を連れて慣れない場所に行くだけでも非常に大変ではありませんか?
子供を連れて行く準備から、慣れない場所での1日がかりの手続きを想像してみて下さい。
「サービス利用計画書」を相談所や指定施設で書いてもらうという事は、子供を連れて行き、子供の特性を説明し、普段の様子を理解してもらい、場合によっては知能テストを受け、今後何が必要なのか相談し、他人にまとめてもらう…ということ。
不安が強い繊細な子を連れて行くだけでも大変なのに、手続きの間中ずっと静かに待ってもらう…んなことできるのか?
それら全てが、順番待ち。仕事と日常の子育てで手一杯なのに無理!
自分一人で、深夜に自宅のテーブルで書類と向き合い、記入するだけで済むのなら、セルフプランの方が楽では?…と考えました。
サービス利用計画書はセルフプランで決定!
前置きが長くなりましたが、ここまでくると他人に任せる方が大変だと思えてきました。
息子が警戒する場所に連れて行き、一緒に行動しながら、本人が気乗りしない何かをやらせ、スムーズにいかない事を周囲に謝りながら進めるより、私一人だけが頑張れば完結する方法の方が精神的に楽です。
しかも苦労して、現地で何時間も待ち、発行までに数カ月待ち、時間を費やすくらいなら。記入の苦労はあっても”待ち”がない方が、療育への道が近くなります。
それらの理由から、私はセルフプランに決定!
サービス利用計画書は自分で書くことに決めました。
セルフプランの「記入例」があれば、セルフプランのデメリットがかなり軽減されるはず。ここから私が自力で頑張ったセルフプランをもとに「記入例」をご紹介します!
サービス利用計画書(セルフプラン)の記入項目
それでは実際に、手元に届いた「サービス利用計画書(セルフプラン)」の用紙と向き合いましょう。
ネット等で調べた他の自治体のフォーマットとも比較してみました。自治体によって項目名は違えど、記入内容としては以下に絞られます。
- 利用者・家族の希望
- 課題
- 目標
- 利用するサービス(事業所)
- 利用頻度
難しそうに見えるセルフプランニングですが、これらの項目が記入できればほぼ完成ということです。
各項目に沿って、記入概要と記入例をまとめます。
【利用者の希望・家族の希望】欄

「利用者の希望」は、利用者が自分で希望を言える年齢であればヒアリングしますが、息子は未就学児(当時5歳)だったため「家族の希望」という視点で書きました。
「利用者の希望」と「家族の希望」は、項目欄が1つの場合があります。私が書くサービス利用計画書では、「利用者および家族の希望」という項目名で一緒くたでした。
この場合、保護者の希望を羅列すれば、違和感はありません。
迷うのは「利用者の希望」欄が独立していて、利用者が未就学児の場合ですよね。省略か?幼児に本人の気持ちを聞くのか?どうするか迷います。
『※可能な場合』とコメントが添えられている親切なフォーマットもありますが、不明点は記入前に、地域の障害福祉課へ確認しましょう。
記入のコツ1:「困り事」を「~できるようになってほしい」に変換する
この後、たいてい同じ書類上に「目標」欄が登場します。「希望」と「目標」の表現は紛らわしく、どっちに何を書くのか分からなくなってしまいますが、ここで深く考えると時間が足りません。
なので、ここでの「希望」欄では、”こうしたい・こうなってほしい”という言い方に徹します。
親の希望を純粋に書くのです。
希望と言っても、目先の困りごとが多すぎて「望む姿」が想像できないかもしれません。
そんな時は、今できない事や困っている事を5つくらい列挙して、それを「~できるようになってほしい。」という言い方に変換します。
例えば、息子の場合。
保育園で「先生の指示が理解できない。皆に向けられた指示を理解していない。」と指摘されたので、
今できない事 =『全体に向けられた指示を理解して行動できない』
これを「希望」に変換すると…
『全体に向けられた指示を理解して、行動できるようになってほしい。』
という感じです。
記入のコツ1:長文?箇条書き?どっちでもいいが…日本語マジック
箇条書きにするのか、ズラズラ文章(長文)にするのかは、正直どちらでも良いと思います。
見やすさを重視するなら箇条書き、困っている感をアピールするならズラズラ書き、という感じでしょうか。
私は「希望」欄では後者で、ズラズラと長文で書く方法にしました。
なぜかと言うと…
この後に登場する「目標」欄では、内容がこの「希望」と似通うことになると思いますが、この時に目標感を出す(アピールする)ためです。
実際には、言っていることは同じでも、「希望」欄はズラズラと長文で想いをアピール、「目標」欄では箇条書きで目標感をアピールするのです!
ここの「希望」欄でも箇条書きにしてしまうと、「目標」欄と比べた時に、まったく同じ内容だという印象を与えてしまいます。
まぁ実際には”同じ内容”なのですが、そこを日本語マジックで違うニュアンスにするのです!
「利用者・家族の希望」の記入例
・〇〇の入学、〇〇での集団生活に向けて、1対多に向けられた指示を理解して行動できるようになってほしい。
・興味のある事に没頭している時でも、時間を見て行動を切り替えていけるようになってほしい。
・今は/今度は/次は何をする時間なのか自ら考え、生活のリズムを作り、学校生活が成り立つようになってほしい。
・視覚優位な特徴を持つ中で、耳から聞く指示や情報だけでも、行動に移せるように訓練していきたい。
・やりたい事とやるべき事が乖離して、感情のコントロールが複雑になる場面でも、癇癪を起さずに行動できるようになってほしい。
・自分の気持ちや状況を言葉で相手に伝えられるようになってほしい。
私が書いた実例です。
5個を列挙すれば、欄が埋まりました。
6個目は欄外。欄からはみ出ましたが、希望が溢れていることが伝わったと思います。
【課題】欄:”できない事”を記入する!
「課題」欄は、自治体によって項目名称が様々でした。
・できない事
・困っている事
・指摘された事
ここでは以下、『課題』とひっくるめて表現します。
「課題」記入のコツ:事実をそのまま困った順に
この「課題」項目の難しい所は、「希望」「目標」の裏返しであること。
さっき「希望」欄で書いちゃったよ!と思うと、筆が止まります。
ここでは、普段できない事を純粋に5個くらい挙げて、その1つ1つで実際に困った場面を伝えるような表現で書きました。
ニーズの優先順位として、課題の「優先順」を示す”番号”を振るようになっている様式も多いので、困っている順に上から書くのがベストだと思います。
同じようなことを「希望」欄に書いてあっても、気にしなくて大丈夫です。
困っている事は事実なので、子供の姿を思い浮かべて、そのまま書きます。
具体的な「課題」が書ければ、それに対応する「目標」が設定しやすいです。
「課題」欄の記入例
私は、6つ列挙しました。
上から順に、ニーズが高い順です。
※「ニーズの優先順位」昇順
| 1 | 母親と離れて教室に入れない。 動くべき時に、すぐ動いて行動できない。 |
| 2 | 警戒心が強く怖がりで、目先の嫌なことを避けて孤立してしまう。 |
| 3 | 行動の切り替えが極度に苦手 |
| 4 | 好きなこと楽しいことは、時間が来てもすぐやめられない。 |
| 5 | 母親と離れること・我慢すべきことがあると「保育園(学校)が嫌だ」に繋がっている。 |
| 6 | 挨拶を恥ずかしがって「おはよう」がスムーズに言えない。 自分の気持ちを言葉で伝えるのが苦手 |
これで、課題が列挙できました。
他にも沢山あるけど、とりえあず代表例を5つ程で良いと思います。
実際の困り順と、少しくらい前後しても大丈夫です。
困った順は、日々違うのですから!
【目標】欄

ここまで出来れば、「課題」に対応する「目標」を整理するだけ。ゴールはもう少しです!
記入のコツ1:課題に対して”出来た姿”を書く
先ほど「課題」を書きましたね?
ここでは、既に書いた「課題」に対する「目標」を書いていきます。
課題に対する目標って?
ズバリ、その課題をクリアして、出来るようになった時の姿です。
今できない事・困っている事については「課題」に挙げたので、今度はそれが出来るようになった子供の状態を書けば、具体的な目標ができ上がります。
記入のコツ2:実際に通う施設の特徴(強み)を意識する
この時、通う予定の療育施設・放課後等デイサービスの特徴を意識して書くと、ポイントが高いと思います。
「この施設のこんな特徴を利用して、こんなふうに成長するんだ!」
「この施設に通うからこそ、これが解決できると思う!」
など、実際に通う(通いたい)施設の強みを利用して、数年後の子供がこうやって成長するんだ!という期待を込めるとベストです。
多くの場合、この「目標」欄と同列で、「通うサービス施設」を書く欄があります。
目標を達成するために通う、その施設と照らし合わせた時に、矛盾せず、納得できる目標になりましたか?
ここで疑問を感じてしまうなら、一旦ストップ!
別のサービス施設を候補にした方が、良いというサインかもしれません。
「この施設の、こういう活動をうまく利用できれば、〇〇が出来るようになりそう!」というビジョンが見えるか?
それが見えたら、「目標」も書けます!
記入のコツ3:短期目標と長期目標は、後から仕分ける
「目標」欄は、短期目標と長期目標とに、分かれていることがあります。
その場合でも、「課題」に対応する「目標」が書けてしまえば、大丈夫。
後から、短期的目標と長期的目標に分ければ良い話です。
療育を始めてすぐに、達成して欲しいこと。目標の中でも一番最初にできるようになって欲しいこと。
そういう目標は、「短期」に振り分けます。
逆に、療育を始めてもすぐには出来ないであろうこと、目標の中でも難易度が高いこと、何年もかけて達成すること。
こういう目標は、「長期」に振り分けます。
「目標」は5~6個挙げたはずだから、それらを2個と3個ずつくらいに分けられるとバランスが良いですね!
「目標」欄の記入例
| 課題 | 目標 | |
| 1 | 母親と離れて教室に入れない。 動くべき時に、すぐ動いて行動できない。 | 慣れた保育園以外の教室に通う。好きな運動を通じて順番や指示を守る。 |
| 2 | 警戒心が強く怖がりで、目先の嫌なことを避けて孤立してしまう。 | 先生の指示を聞きながら、安全で正しい方法を理解して挑戦する。 |
| 3 | 行動の切り替えが極度に苦手 | 先生の指示を理解して、今やっている事をやめる練習、次やることに移る練習をする。 |
| 4 | 好きなこと楽しいことは、時間が来てもすぐやめられない。 | 時間を見て次の行動に移る。癇癪を起さずに行動する。 |
| 5 | 母親と離れること・我慢すべきことがあると「保育園(学校)が嫌だ」に繋がっている。 | 「嫌な事=できない事・怖い事」を少しでも減らすため、運動プログラムを通じて自信をつける。 |
| 6 | 挨拶を恥ずかしがって「おはよう」がスムーズに言えない。 自分の気持ちを言葉で伝えるのが苦手 | 不安も混じる難しい朝のスタート「おはよう」が自然に言える。 終わりの合図、気持ち・状況を言葉で言える。 |
表内の太字は、息子が通う予定のサービス施設を意識した部分です。
その施設では、運動プラグラムを中心で、「動」と「静」を意識しながら、行動を切り替えていく療育プログラムを採用しています。
「動」の活動では、待つ・動く・終わって待つ、「静」の活動では、静かに集中・終わったら自分で合図、などの行動療育です。
そういう施設の特徴を活用しながら、その目標を達成していくイメージが沸くように、目標を挙げていきました。
「短期目標」「長期目標」の記入例:言い回しを変えて、達成期間を添える

ここまで「希望」「課題」「目標」を書いてきたので、目指すところが見えてきました。
「希望」や「目標」に書いた文章をピックアップして、短期間でできそうな事と長期間かかりそうな事、大きく2つに分類しました。
なかなか出来そうにない目標を「長期目標」として、すぐ~半年後くらいにできそうな目標を「短期目標」に分類できたと思います。
最後に、「短期/長期」の区別がより分かりやすいように、言い方を変えてみましょう。
「短期目標」は、『〇〇を少しずつ(一部が)できるようにする。」
「長期目標」は、『〇〇ができる。』という表現に変えると、それらしくなります。
短期目標は、半年ごとに見直すはずです。
先々を心配してあれこれ考えず、現在を中心に考えれば大丈夫です。
加えて、達成期間の目安を書けば、完璧です!
例)(半年~1年)、(3か月~6ヶ月)など
【利用するサービス(事業所)】欄
「サービス利用計画書(セルフプラン)」の用紙を書き上げる頃には、「利用するサービス施設(事業所)」が概ね決まっているはずです。
あるいは、見学中かもしれません。
決まった時点で、実際のサービス施設名を書き込みます。
前述の通り、「目標」まで書き上げるためには、利用するサービスが決まってからの方が、記入しやすいです。
★利用するサービス(事業所)の選定は、私なりに迷いました。その気持ちは長くなるので、別記事でご紹介予定です。
【利用頻度】欄を記入する
サービス利用計画書(セルフプラン)記入のコツ。
最後にお伝えするのは、利用サービス(事業所)の「利用頻度」です。
どの自治体の「サービス利用計画書」フォーマットにも、必ず書く場所があります。
「利用頻度」記入のコツ1:月単位で最適な回数を考える
息子は、あんなに嫌がる保育園に対してでさえ、所属意識が芽生え始めました。
なので、息子にとって療育は、保育園を休んでまで行く所・週に何回も行く所というイメージではなく、週に1回~多くて2回の習い事感覚で、午後から行けるプログラムが希望でした。
そこでセルフプランの「利用頻度」欄に最初、『週1~2回』と書いて申請したのですが…!
役所の窓口で、「ひと月に何回か、で書いてください」と言われて、その場ですぐに差し戻されました。
利用頻度は、月に何回利用するのか、月ベースで書きます。
毎週?隔週?週に何回?5週ある月はどうする?
実際に通う場面を想定して、月単位で何回の通所が理想なのか考えます。
「利用頻度」記入のコツ2:実際に通う回数より”多め”に書く!
窓口で申請する時に、もう1つ言われた大切なことは、「実際に通う回数より、余裕をもって、多く書く」です。
この「利用頻度」は、通所受給者証に記入される「支給量」。
支給量を超える回数で、施設を利用することはできません。
通所受給者証の「支給量」欄には、この「利用頻度」に書いた回数が、そのまま掲載されます!
通いたいと考えている目安の回数、最低回数、最大回数があると思いますが、そのうち、「最大回数」もしくは「それ以上の回数」を月単位で記入して下さい。
あと超注意点は、「複数の施設に通う場合の支給量」です。
例えば、今はA施設に週2回の通所と考えて、月単位で利用頻度は「平均8回」、「最大でも10回」だと想定して申請し、「支給量:月10回」となった場合。
後から、B施設にも月2回の通所を追加したら、月トータルで「11回」になってしまう月があり、当然、(助成金を利用しての)通所は許可されない!
という事例があります。
「サービス利用計画書(セルフプラン)」記入例まとめ
実際に記入する上で分析し、実際に書いて、実際に申請して、2週間で発行された通所受給者証。
この時の「サービス利用計画書(セルフプラン)」について、コツと記入例をまとめました。
整理すると・・・
- 「希望」は、困った事・できない事を「~できるようになってほしい」という言い方に変換する。希望を純粋に書く。日本語マジックを使えば、他と内容が重複しても大丈夫。
- 「課題」は、困っている事を実際にあったような表現で書く。優先順位を付けておくと書きやすい。
- 「目標」は、課題をクリアした時の姿を思い浮かべて、課題に対して、出来ている姿を書く。難関な目標は「長期目標」、現在を中心に考えて少しずつクリアしていく目標を「短期目標」として仕分ける。
- 「利用頻度」は、実際にサービス施設(療育施設・児童発達支援・放課後等デイサービス)を利用する回数より、多く書く。
です。
皆様のセルフプランが上手く書けますように。
お子様に合った療育に出会い、少しでも過ごしやすく生きやすくなりますように!
私が書いた息子のセルフプランが、少しでも参考になれば幸いです。
※お住まいの地域によって、必要な書類や申請方法が異なる場合があります。
※利用するサービスによって、必要な書類や申請方法が異なる場合があります。
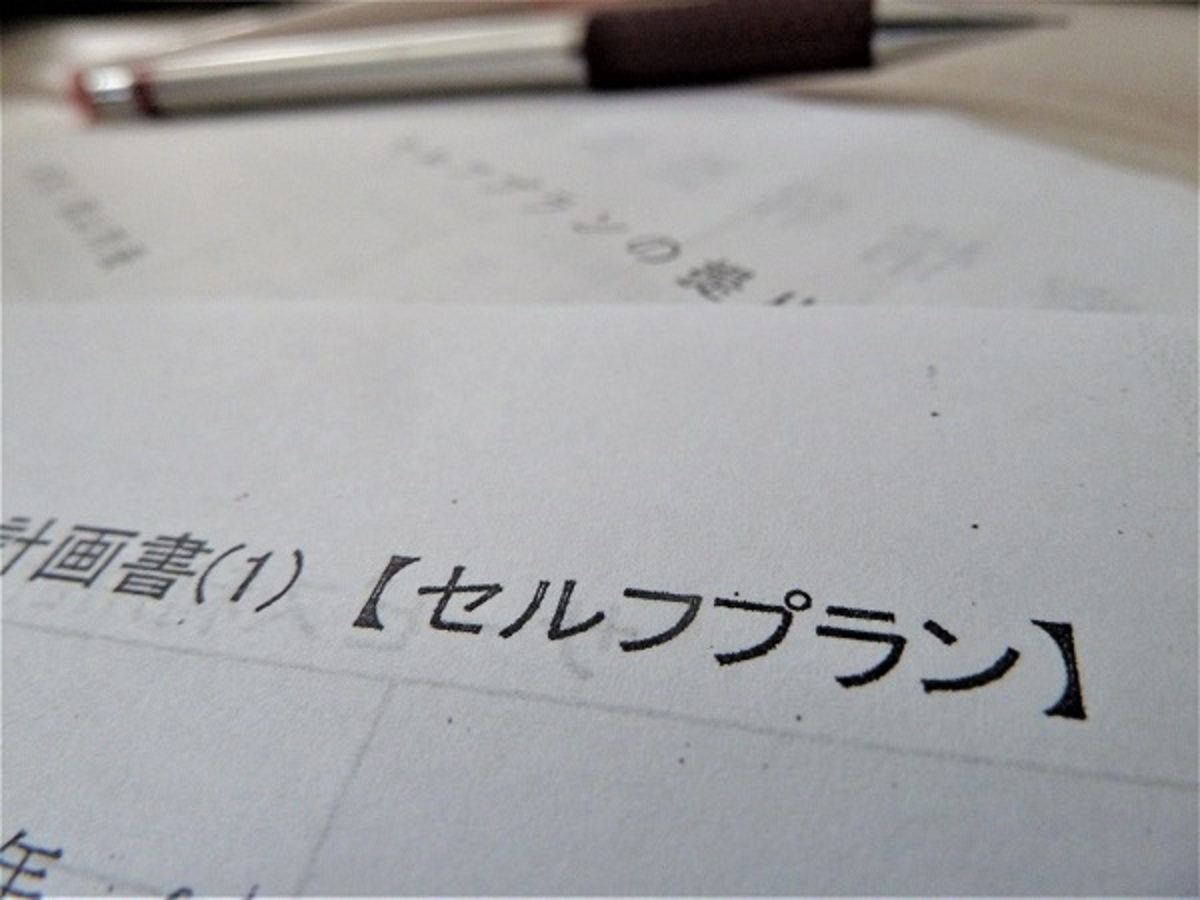
















コメントを残す