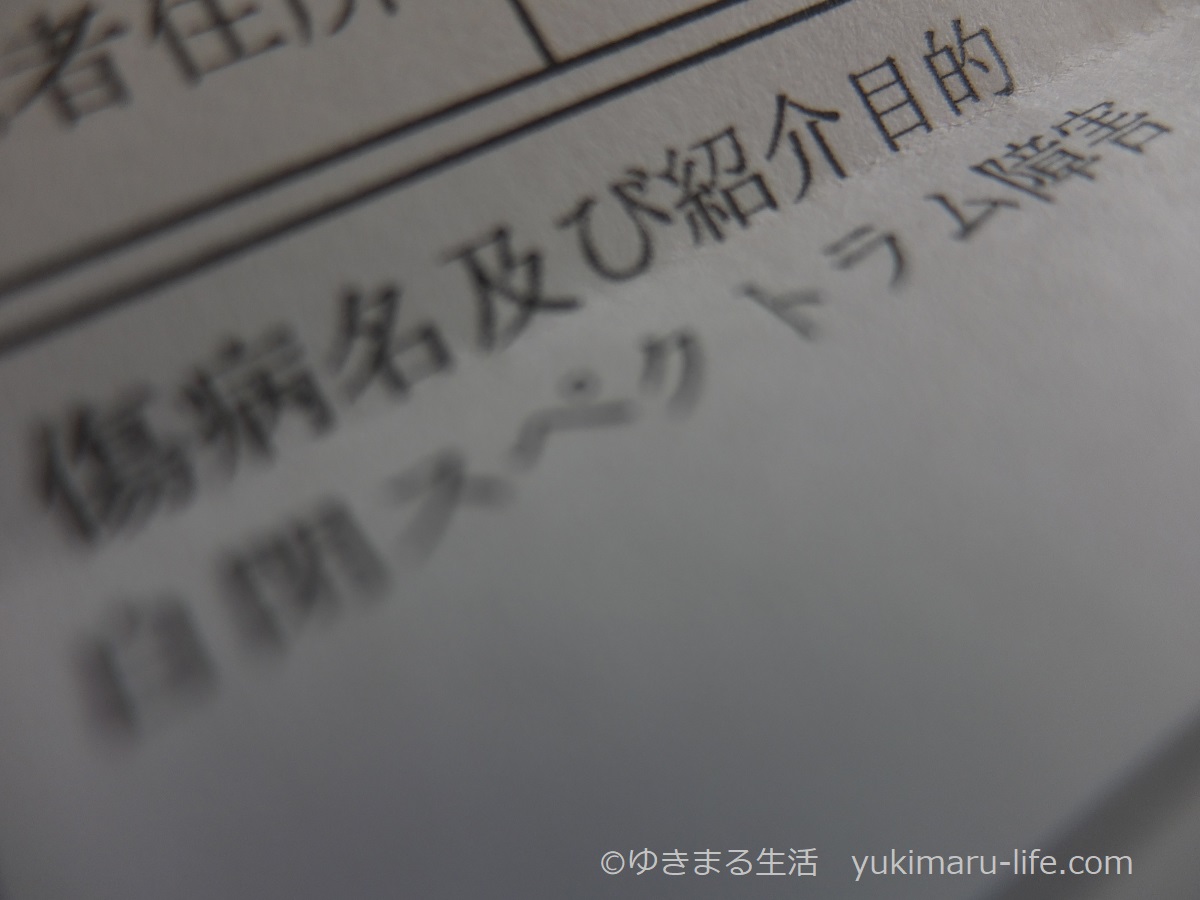療育施設の通所に必要な「受給者証」。申請には「医師の意見書・診断書」が必要だったため、かかりつけ小児科で相談することに。
かくして”いつもの小児科”で発達相談することになり…。
いよいよ「医師の意見書」を入手します!
小児科の主治医には断られたが…
息子には喘息の定期通院をはじめ普段から通っている小児科があり、そこの主治医に「療育に通うために診断書(意見書)をもらえないか?」と相談しました。
ところが、先生は発達専門ではないし、グレーゾーンを確定診断する責任は負えない…ということで、断られました。
※詳細は、別記事(上記)ご参照
療育センター長も兼任している「専門医」が診てくれる!
しかし、非常勤として手伝いに来てくれている先生が、別の地域で「療育センター長」だそう。
その先生が次回来るタイミングに合わせて、「発達相談」として予約を入れてくれました。
こうして、この行き慣れた小児科クリニックにて、別の地域で療育センター長をやってる先生(以下「専門医」)と発達相談できることになりました。
主治医の先生が「早い方がいいでしょう?」と気を利かせてくれたこともあり、予約は来週というスピード感。この時点から1週間もありませんでした。
発達障害(特徴・特性)チェックリストを作成

急きょ実現する「専門医との発達相談」に向けて、発達障害のチェックリスト作りを作りました。
そのまま使える理想のチェックリストが見つからず、自作しました。
※上記は、実際のリストの一部
発達支援を行っている企業のサイトで公開されている「発達チェックリスト」や書籍内に掲載されている「特徴リスト」類をピックアップして、特性チェック項目をExcelファイルに一覧化しました。
各特徴/特性に対して、息子が該当する/しないを3段階(○△×)で評価。
具体的にどんな状態なのか、どんな特徴が目立つのか、等の特記事項をメモしたものです。
発達障害(特徴・特性)チェックリストの使い方
私が自作した発達障害チェックリストは、A4紙びっしり6ページ。
全部に目を通してもらえないのは想定内。
でも、これだけの項目に対して、これだけの「〇」と「△」が並んでいて、「こんなに当てはまるんです」と専門医に見せれば、療育が必要な状況はすぐに伝わると思いました。
それからチェックリストの余白には、
『保育園で指摘』『行動の切り替えが苦手』『母子分離不安』『感覚過敏』『強いこだわり』
と、息子の特性キーワードをメモしました。
発達相談の当日、このメモがけっこう役に立つことになります。(後述)
発達の専門医は、息子が知っている先生だった…
発達相談の当日。
別の地域で療育センター長をやっているという先生に会いました。
息子がその専門医を見るなり、「注射しない?」「注射しない?」「注射しない?」と連呼してプチパニックになってしまい、おかしいな?と思ったら…。
なんと、この年に息子のインフルエンザ予防接種をしてくれた先生でした。
(既に出会っていたんだなぁ~)

息子が、予防接種してくれた先生の顔を覚えていたことに感心しつつ、今日は注射しに来たのではないと改めて説明しました。
息子はいつもと違う雰囲気を感じ取ったのか?
すっかり大人しく静かになって、後ろのスペースで遊び始めました。
専門医(療育センター長)と発達相談!

普段、どんな感じなの?
息子が普段どんな感じなのか?を聞かれたため、これまでの経緯と目立つ特徴(特性)について答えました。
- 保育園での集団生活について行けていない、と指摘を受けた
- 「行動の切り替えが苦手」で、やりたい事ができない時ややめる時に癇癪を起す
- 「母子分離不安」の傾向があり、母親と離れて別の場所に行ったり、新しいことをしたりできない
- 「感覚過敏」「聴覚過敏」の傾向があり、怖い時に耳をふさぐ
- 「こだわりが強い」傾向があり、片手に収まるオモチャ1つを必ず持って行動する




ここで持参した「発達障害チェックリスト」が役立ちました。
先生も手にしてパラパラと目を通してくれたし、自分で余白にメモした特性キーワードを見ながら、言い漏れないように確認できたからです。
発達が気になる子の”診察中の様子”
先生は、私が渡した「チェックリスト」をパラパラ見ながら、私の話す息子の特徴を聞きながら、実際にそばで1人で遊んでいる息子の様子をチラチラ見ていました。
1人で遊んでいて、何か見てほしい時や呼んでもすぐ来てもらえない時に、息子が「こっち来て」「ねえ、見て」「一緒に〇〇やろー。」と言って来る姿を見て、何かを感じたようでした。
ASD(自閉症スペクトラム)の診断で質問されたこと
さすが専門医?
先生は、特性を捉えるにあたり、もう何を聞けば判断できるのか分かっているような雰囲気で、質問がポンポン来ました。
私はそれにポンポン答えました。
Q「保育園で友達と遊んでる?」
A はい。
Q「友達といる方が多い?一人でいる方が多い?」
A 一人でいる方が多いです。
Q「服とか手が汚れて、ものすごく嫌がる?」
A 手に付いたベタベタや汚れは、すぐ洗いたがります。
Q「何かをすぐ並べる?オモチャとか並べる?」
A 最近はそうでもありませんが、もっと小さい頃は、ミニカーやプラレール等の乗り物系のオモチャをよく並べていました。
Q「あまり寝ない?」
A あ…はい。小さい頃は、音に敏感で夜中もすぐ目を覚ましました。最近は、夜中に起きることはありませんが、寝つきがスゴく悪いです。夜だけじゃなく、昼寝も、寝つきが悪いです。
発達障害(ASD:自閉症スペクトラム)「あるかもねぇ~」
「ちょっと(発達障害・自閉症スペクトラムの可能性が)あるかもしれないねぇ。」
一連の確認が終わると、先生は「ちょっと、あるかもしれないねぇ」と言いました。
「発達障害」とか「自閉症スペクトラム」という単語は、はっきり言葉にされませんでした。
この反応に賛否両論はあるかもしれませんが、この時のこの場では…
「さすが、数分見ただけで分かっちゃうんだ…」という感想でした。
意見書「児童発達支援施設の利用は有効である」をゲット
先生:
「知的障害なし。軽度と捉えて。
そういう傾向は、大きくなるに連れて改善されていくから。
でも、『決まり文句』で書かなくちゃいけないから、ただの『決まり文句』だと思ってくれていればいいから。」
そう言いながら、作成された書類には、
傷病名及び紹介目的:自閉スペクトラム障害
社会性やコミュニケーションの発達に遅れがあります。児童発達支援施設の利用は本児の発達促進のために有効であります。
と書かれていました。
なるほど、これが『決まり文句』のようです。
「療育は早いうちにやった方がいい」メリット/デメリットの話
先生:
「療育プログラムを受けることは、デメリットはなくてもメリットはあるよ。
メリットがなかったとしても、デメリットはないよ。
効果が出るか出ないかは、その子によって違うけど、「やって後悔」するより「やらなくて後悔」する方が、断然多いよ。
だから、やっておいた方がいいと思う、それも早いうちからね。」
先生は、療育に通いたいという私の意見に賛成していました。
※この時から約6年後、息子が小学校高学年で不登校になったことを機に、私は特性の矯正や自分を壊してまで「普通に合わせること」に大きな疑問を持ち始めます。
※その子に合った早期療育がメリットなのは確かですが、合わない or 適当 or 金儲け主義なだけ or「普通に合わせさせるだけ」の療育はデメリットになると思っています。
「療育(児童発達支援)への道」がはじまる
こうして、「医師の診断書/意見書」(実際の書類名は「診療情報提供書」だった)を入手することができました。
療育(児童発達支援)への道が少し縮まり、達成感がありました。
次の山場は、もう1つの申請書類「サービス利用計画書」、通称「セルフプラン」の作成です。