始めての療育施設の見学。私1人で見学しただけでは、いざ実際に息子が過ごすイメージが具体化できませんでした。
日を改めて、息子を連れて、療育施設の見学&体験に訪れました。
知的障害を伴わない、自閉症スペクトラム傾向にある息子が、療育プログラムに参加するとどうなるのか?参加して見えてきたこと、分かったことをまとめました。
「個人に合わせたプログラム」の意味って?
多くの療育施設が、パフレットやHPでは「個人に合わせたプログラム」と謳っています。この日、見学した療育施設もそうでした。
でも、多くの場合、完全な個人型・マンツーマンタイプのプログラムではなく、グループに分かて活動するタイプのプログラムです。
それはある程度、始めから知っていたのですが、想像していた以上に「グループ活動」でした。
では、どこが「個人に合わせた」部分なのか?
年齢や得意/不得意分野を考慮して、グループ分けされる。その子の目指すゴールを意識して指導される。この点は、確かに「個人に合わせて」いました。
完全なマンツーマン指導でないことは分かっているのですが、目の前で繰り広げられた「グループ活動」のレベルであれば、通っている保育園の集団生活の方がトレーニングになっている気もします。
療育施設によって、差が出てくるところ。「グループ活動」のレベル具合を見極める必要がありそうです。
個人に合わせて「やる気」を引き出し、肯定感を高めようとしてくれる。
とはいえ、保育園の集団生活よりも優れている部分もありました。
例えば、マット運動。
年齢や特徴から判断して、身体を動かすことが不向きな子は、別の部屋で絵本を読む別グループへ移動しました。
身体を動かしながら活動するグループは、マットの準備をしてから、順番にゴロゴロ進行や前転をする練習が始まりました。
向き・不向きに合わせて、グループ分けしてくれることが明確でした。
「マット運動」グループでは、一人一人のレベルに合わせて挑戦させていることも分かりました。
「一度できなくても諦めずに挑戦する」という姿勢をゴール&療育プランとしている子は、前転が一度できなくても「〇〇くん!がんばれ!もう一度やってみよう!」と励まされ、挑戦を促されていました。
「1つ1つはできなくていい、皆と一緒に行動する」ということがゴール&療育プランの子は、前転ができなくても「〇〇くん!すごい!そこまでできた!」と褒められていました。無理強いはされず、皆と一緒に並んで順番を待って自分の番で動き出せたことでOK、という具合です。
息子が参加したのは、マット運動のグループでした。
始めての場所で、私から離れる事を不安がり、最初は参加できませんでした。
でも、先生がその様子をみて、私のそばにマットを近づけてくれました。その途端、不安要素は消えたので、息子はやる気マンマンで前転をし始めました。
個人のタイプに合わせた活動&方法が工夫されていました。
保育園の集団生活では「遅れをとる子」に対するケアとして、ここまで対処されないから、「さすが療育」という印象でした。
ただ、療育施設を決めるにあたって、まだ確信が得られません。
既に保育園でもっと過酷な集団生活に揉まれている息子にとって、療育活動の内容全体が、価値あるものか見極めないといけません。
保育園を休んでここに来る意義はあるのか、息子にとって有効なのか?
まだそれを見極め切れてません。
他の子の”特性”が療育活動に大きく影響
療育施設に限らず、どこへ行っても影響すること-。
それは、想像していたけど、やはり「他の子」です。
息子が療育体験に行った日は、同じグループの中に6歳の女の子がいました。
その子が、事あるごとに息子に対して「なんで新しい子が混ざるのよ!」「新しい子は来ないで!」と叫ぶのです。
息子は、内心傷ついてもヘラヘラして引きつった笑顔を見せるタイプだから、泣いたり活動を止めたりはしませんでした。
その言葉にあまり反応せず、ニコニコしながら皆に着いて行っていました。
でもこれが、毎回そうだとしたら、きっと「来ないでって言われるから、イヤだ」と言い出すに決まっている。
どんなに療育プログラムに賛同しても、やはり同じ部屋・同じクラス・同じプログラムに一緒に参加するメンバーも重要だと悟りました。
プログラム内容と同時に、一緒に過ごす他のお友達のタイプも把握してから判断すべきだと学びました。
参加する時間帯や曜日を選べる施設なら、それぞれの様子を把握してから判断するのが良いと思います。
体験しないと分からない!聴覚過敏な子に重要な「音環境」
部屋の広さ、人数、先生や生徒のテンションにも左右されると思いますが、重要な要素として気が付いたことは「音環境」です。
見学前には気が付けませんでした。
CDプレイヤーから流す音楽の音、先生の大きな声、他のお友達の叫び声。
これらが混じり合い、私の第一印象は「やかましい」です。
部屋の片隅に、両耳をふさいで座る男の子がいました。
ああ、きっと、この音量と先生の声が頭に響くんだろうな…。
同じく聴覚過敏の息子は、この時の体験入園では、テンションが不自然に上がっていて、不自然にはしゃいでいました。
落ち着いている時や、イヤイヤ登園した時に、この雰囲気の部屋に入れと言ったら、息子も”あの片隅にいる男の子”のように、耳を塞いで嫌がるかもしれない。
様々な特性を持つ子供たちが集まるから、先生たちも興味を惹き付けようと必然的に声が大きくなっていました。
先生たち自身がテンションを上げ、掛け声というか励まし声というか、とにかく大きな声で話します。
そこにちょっと大きめの音楽と、ボリュームお構いなしに叫ぶ子の声。さほど広くない部屋に響き渡り、騒々しいワンルーム状態でした。
息子が居心地がいいと思える環境とは、ちょっと違う気がしました。
…体験入学の時の息子のテンションは、普通じゃない。
これは、まったく同じ場面を「英会話教室」で経験済み。
無料体験では不自然な高いテンションではしゃぎ、「楽しかった!」と言う。いざ入学したら、教室にすら入れなかった・・・という苦い経験は、「英会話教室」で実証済みです。
療育施設選びでは、音楽環境を含めた雰囲気、テンションが下がった時に参加できるか、なども考慮しなくてはいけないと思いました。
言うことがコロコロ変わる!?民間療育のセールストークはうまく見抜いて
園長先生の話っぷりについては、別記事でも触れました。
徹底的な違和感となったのは、セールストークです。民間療育、特有なのでしょうか?
療育施設に入園するためには、様々な書類作成・申請・受給者証の取得などが必要です。
一般的に、保護者だけでは難航するそれらの書類準備について、私が一人で話しを聞きに来た前回は、「ボランティアになりますが、療育プランに関わる部分は、こちらで下書きとして埋めるから大丈夫です。」という言い方でした。
ところが、息子と一緒に来た今回は、「基本はご自分でお願いします。皆さんそうしてますから。」という言い方でした。
通所を迷っている前回と、通所しようかという姿勢を見せた今回で違うのか?
定員に満たず新入生が欲しかった前回と、定員オーバーで調整が必要になるから新入生は入れたくない今回・・・という裏事情なのか?
その違いの真相は、よく分かりません。
見学を終えて、市役所に連絡したり書類を取り寄せたりと、「療育への道」と題して、前に進み始めました。
しかし、やはり何か引っかかる。
仕事で忙しくて事前に充分に相談できなかった夫が帰宅した時、さすがに療育を通いを決めるに当たって言っておかないと・・・と思い、見学に行った療育施設の園長に言われたこと等を話しました。
するとピタっと立ち止まり「辞めたら?そこ。印象悪いよ。」の一言。
(そういう所は、迷いもせずに言うのね。)
でも、なるほど。
父親の直感というものも、大事にした方がいいのかも。
進むべき道を再び迷い始めた私は、もとい、半年前に色々相談に乗ってもらった発達支援センターのカウンセラーに相談を求めて連絡しました。
そのカウンセリングで、ズバリ的確なアドバイスを受けることになります。
「民間療育は有効だけど、セールストークはうまく見抜いて。」 と。
民間療育の場合、儲かる/儲からないの定員ラインもあるだろうから、入所して欲しいタイミングが明確にあるのかもしれない。
見学する時は、セールストークを見極めないといけないなと思いました。












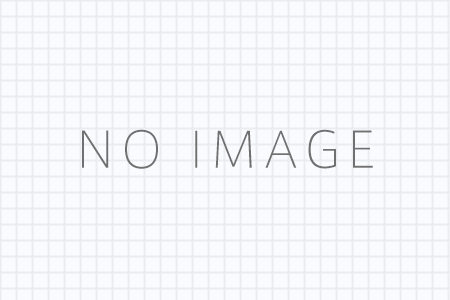





お気軽に感想・質問・記事リクエストなどをどうぞ。コメントは内容確認後、お返事と一緒に表示されます。