食物アレルギーがあると、一般的な就学準備の他に「学校給食のアレルギー対応」について考えなければいけません。
噂やSNS上の話だけでは、実際の自治体も小学校も違うため、情報に煽られて翻弄するだけ。
闇雲だった小学校の「食物アレルギー対応」の”実態”が、身近なものとして捉えて課題を直視できたきっかけ。
それが、教育委員会が定めた「学校給食における食物アレルギー対応ガイドライン」を読んだことでした。
まずは「学校給食の食物アレルギー対応ガイドライン」を読む
息子は就学当時、小麦・乳・ゴマ・ナッツ類の複数のアレルギーがありました。(今もだけど)
食物アレルギー対応に恵まれた保育園時代とは違い、小学校給食のアレルギー対応は厳しいと聞く…。
沢山のアレルギーを持っていたり、重度だったり、エピペンを持っていたり、過去にアナフィラキシーショック経験があったりすると、学校給食は食べられないのか?
何も分からない状態から抜け出すため、行動に移したことの1つが、教育委員会が定める「学校給食における食物アレルギー対応ガイドライン」を読むことでした。
実際に、自分の子供が通う小学校の管轄の教育委員会。そこが基本ルールとして定めているガイドライン。これを読むことで、
・実際に何がモヤモヤするのか
・実際に何が分からないのか
・実際に何が課題なのか
頭の中が整理できました。
除去は「卵」だけ!?対象アレルゲンの少なさにショック…
最初にショックが隠せなかったのは、除去対応の基準についてです。
アレルギー特定原材料7品目のうち、「卵」については可能な範囲で除去対応、「乳・小麦・そば・落花生・えび・かに」については弁当対応
「学校給食のおける食物アレルギー対応ガイドライン」より抜粋・要約
た、タマゴだけ!?
おかず一品を作るのに、小麦・乳成分を含めないって難しいです。
この時点で、ほぼ毎日「弁当持参」になります。
しかも、「卵」以外は除去対応しないということは・・・
7大アレルゲンフリーのはずだった”おかず”の上に、小麦たん白を含む”かまぼこ”が添えられただけで、その一品は弁当対応になることを意味します。
全ては「現場の混乱」と「児童の安全のため」という何でも解決できる魔法の言葉で締めくくられ、理解するしかありません。
※教育委員会に疑問をぶつけたこともあります。
飲用牛乳の停止、揚げ油の扱い、年間弁当…補足事項にご注目!
更に、ボディーブローのように、「ショッキング・ザ・ガイドライン」が効きました。
乳アレルギーの場合は、飲用牛乳の停止はするが、除去食は提供しない。
「学校給食のおける食物アレルギー対応ガイドライン」より抜粋・要約
”7大アレルゲンのうち「乳」は、除去対応しない”ということは、既に分かりましたが、「牛乳パックは停止しても、除去食は提供しないよ。」と念押ししています。
揚げ油の共用により影響が心配される場合は、年間を通して弁当持参とする。
「学校給食のおける食物アレルギー対応ガイドライン」より抜粋・要約
「揚げ油の共用」がNGの場合は、その日が弁当対応になるどころか、驚きの「年間通して弁当」だと言っています。
理由は、揚げ油は再利用することがあるから、だそう。
小麦アレルギーとしては、揚げ油を使った後に”こして”いるのか、網でパン粉を簡単にすくっただけなのか。
これによっても大きく判断が変わりますね。
パン粉が大量に浮遊する揚げ油の中に、素揚げする野菜を投入するような場面があるのでしょうか。
もしも「あり得る」と言われたら、息子も「年間通して弁当」対応になる可能性が出て来ました。
過去のアナフィラキシーショック経験が足枷に?
病院のアレルギー科の初診時も、旅行の宿泊先のアレルギー対応問合せ時も、そして学校給食の実態調査表でも、必ず聞かれるのが「アナフィラキシーショック経験の有無」です。
管理指導表で「アナフィラキシーあり」の場合、コンタミネーションや微量のアレルゲンで反応する可能性がある児童生徒は、給食の提供はしない。年間を通して弁当対応とする。
「学校給食のおける食物アレルギー対応ガイドライン」より抜粋・要約
学校給食における食物アレルギー対応ガイドラインでも、過去にアナフィラキシーショック経験がある児童生徒は要注意!という項目がありました。
これについては、更に条件分岐があり、”微量のアレルゲンでは反応しないと判断された児童生徒には、該当アレルゲンがない日は給食を提供する”…とありました。
息子は、アナフィラキシーショック経験あり。
しかしながら、年齢と共に抗体数値も下がり、経口免疫療法を進めていることもあり、現在コンタミは気にしていないアレルギーレベルです。
「微量でも反応するか?」という問いに、「いいえ」と答えられないのは、ナッツ類か。
コンタミネーションや微量アレルゲンで、アレルギー症状が出ない体質にしていくことが、今後も重要になります。
経口免疫療法は引き続き進め、アレルギー症状が出ない摂取量(閾値)を少しずつ上げていくことは、意味のあることだと思えました。
代食(弁当)でも給食費の返金なし!
弁当持参や除去食による食材の返金は行わない。
「学校給食のおける食物アレルギー対応ガイドライン」より抜粋・要約
ガイドラインでは、「弁当持参による食材の返金なし」という掲載がありました。
除去対応される学校の場合は理解できるけど、ほとんどのメニューが代替弁当になるのに、給食費を皆と同じように払う…というのも、最初は違和感がありました。
アレルゲンに応じて「何%割引」とか定められていれば良いのに。
早めに覚悟できる!ガイドライン事前読みのススメ
A4用紙7ページにまとめられた「学校給食における食物アレルギーガイドライン」が、ざっと読み終わりました。
「毎日弁当」を覚悟するしかないかな?
覚悟しながらも、アレルギー対応面談の時には、
- 「年間通して弁当」ではなく、毎月の献立を確認した上で、日毎に「給食 or 弁当」を決めたい。
- 「白米」の日は、「白米」を提供してもらい、「おかず」だけ弁当持参にしたい。
ということを相談したいと思います。
アレルギーがある児童は年々増加傾向。アレルギー原因食品が多種にわたる時代背景もあり、教育委員会が把握している現況だけでも、該当アレルゲンが「62種類以上」に及ぶそうです。
個々のアレルギー対応は難しい状況であることが分かります。
アレルギー児の就学に向けて、管轄の教育委員会が定めている「学校給食の食物アレルギー対応ガイドライン」を事前に読んでおくのがお勧めです。
アレルギー対応として、何が期待できて、何を諦めるべきなのか、概要を知ることができます。
私の場合、実際に入学説明会でガイドライン(簡易版)が配布されて読んだ時に、既に概要を知っていたので、それほど驚かずに済みました。
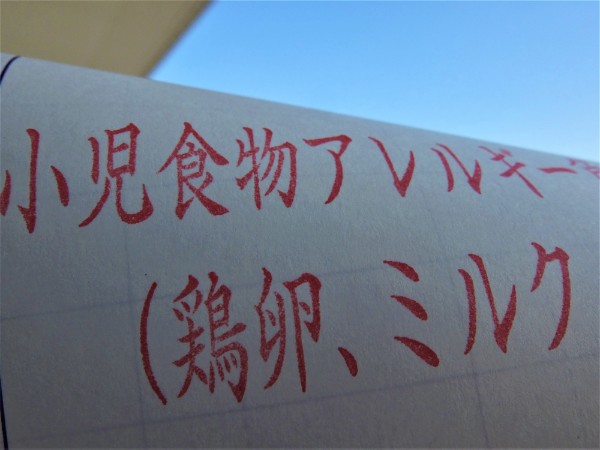

















ちょうど私もタイムリーに就学前検診で栄養管理担当者さんと話す機会があるので、話し合ってきたところです。
が、健康診断を受けるだけだと思って準備をしていなかったので(別途相談に来てくださいと言われていたので)、今幸さんの記事を読んで「はっ、揚げ油のこと聞き忘れた!」と気付いた次第です。
他にも聞き漏れがありそう…。
気付かせていただいてありがとうございます。
卵以外の除去はないとは、ちょっと配慮が足りなさすぎですね。
とはいえ、私の自治体でも小麦は麩・ワンタンの皮・マカロニの3つだけが除去可能で、それ以外のおかずは一切は提供できないとなっていましたが…
まさしく、かまぼこ1個で食べられない状態です。
ですが、本当に「文部科学省のガイドラインに則って」いるなら、少なくとも自治体によって大きく差が開くといった事態は起こらず、ある程度同じような基準で提供できるのでは、と思ってしまいました。
今は普通のスーパーで、アレルゲンが入っていない食材が手に入りやすい時代。
調理中の除去は難しくても、最初からアレルゲンフリーの食材で全児対応するなどで、事故防止しながらみんなで食べる方法もあるはずです。
きっと、もっとアレルギー児に寄り添った給食提供をしている自治体もあるはずです。
本当に保育園では恵まれていて、アレルゲンがあっても基本はみんなと同じメニューで、麺類とかパンみたいなそれ自体がアレルゲンの場合でもご飯を用意してくれたりと、とても手厚かっただけに小学校の給食対応には結構動揺しています^^;
でも、さすがにうちの市でも提供しない分については減額してくれるらしいので、幸さんがこの件でモヤモヤするのは当然です!
安全優先というのはもちろんわかりますが、教育委員会に物申せる機会があるなら、そのあたりは家庭の意見を伝えないといつまで経っても対応が変わらないんじゃないでしょうか…。
…話は変わりますが、今週1度目の食物負荷試験を終えて、無事戻ってきました。
血液検査で数値に表れていない卵黄の試験だったので当然といえば当然ですが…。
来週から家庭での経口免疫療法をしていくことになりました。
その際はいろいろアドバイスいただき、ありがとうございました。
幸さんのブログを何度も読み返し、心の準備をして臨んだおかげで、忘れ物もなくスムーズにいきました。
次は本命の卵白なので、またブログで復習しつつ、頑張ります。
>こゆりす さん
コメントありがとうございます。
私も時々、ブログを読ませて頂いています。
就学に向けて、少しずつ準備が進んでいるのですね。
「文部科学省のガイドライン」は、最近のアレルギー事情をよくまとめて反映されているのですが、捉え方次第で、どうとでもなってしまうんです。
『大原則』として、「全ての児童生徒に給食を提供する」と謳っていても、同じレベルで「調理現場で無理はしない」的な指針も盛り込まれています。
これだと、「うちの学校(自治体)では、調理現場の人材も限られているから無理」という方向になってしまい、まぁ想像通りの結果になっています。
食物負荷試験、お疲れ様でした。
卵黄の経口免疫療法に踏み込めて良かったですね。
卵は、食品への含有率が高いから、経口免疫療法に入ることが正解だと思います。
卵白は、「生のドロドロ」と「固ゆで」の状態でも症状が変わってくると思います。
まずは「固ゆで」がほんのちょっぴり、食べられると良いですね。
私(の息子)は、次回「ピーナッツ」負荷試験のリベンジです。
(前回の負荷試験で失敗している)