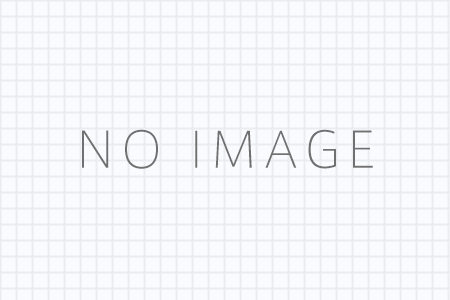保育園。夏が来れば「お泊り保育」がやってくる!
不安が強く、母子分離不安もあって一人で眠れない、夜だけオムツだし、おねしょも心配…。息子が親と離れて保育園にみんなと泊まるなんてできるのか…。
心配だらけだった「お泊り保育」ですが、成功の鍵は2ヶ月前から始めた事前準備でした。
不安が強い保育園児って?
息子は、不安がとても強く、予定や見通しが分からないと先に進めない子です。
この後何が起こるのか、これから何をするのか、事前に説明して把握しなければ安心できないのです。
不安が大きいままだと、できるはずの事も遅れたり出来なかったりして、余計に状況が悪くなってしまいます。
おまけに、母子分離不安もあり、母親と離れることを極度に不安がり、夜一人で寝るなんて出来そうにない…。
そんな息子が5歳の時、保育園生活で最大の試練!?「お泊り保育」がありました。
保育園の「お泊り保育」とは?
息子が通った保育園では、保育園最後の5歳児クラス(幼稚園でいうと年長クラス)の夏に、「お泊り保育」という宿泊イベントがありました。
※「お泊り会」と呼ぶ園もあります。
保育園生活の6年間で最後の年に一度だけ、かつ宿泊を伴う行事なので、保育園行事の中でも「一大イベント」という位置付けでした。
保護者とは別に、先生と友達だけで、夕食から翌朝までを保育園で過ごします。
親と離れて「初めてのお泊り体験」となる子供も多いし、いつもの「お迎え」がなくそのまま園に滞在するため、親子共々ドキドキでした。
「お泊り保育」のお知らせは、けっこう直前
5歳児クラス恒例行事、お泊まり保育までいよいよです。
「お泊まり保育のお知らせ」より抜粋
保育園で夕食を作ったり、花火をしたり、様々な経験を積みます。子どもたち同士で過ごす一日は、きっと絆を強くし、また1つ成長してくれるでしょう。
お泊り保育まで「あと2週間」となった時に、保育園から保護者宛てに「お泊まり保育のお知らせ」が配布されました。
一大イベントのお知らせタイミングとしては、けっこう直前…という印象。
何も知らされなくても「保育園で夕食を食べて、皆で遊んで寝て起きる…」という想像はできていましたが、お知らせをもらって初めて具体的に「夕食を自分たちで作る」「花火をする」等の内容が見えてきました。
先行き気にして心配しちゃう子は、詳細予定を別途確認しておく
ただ、全体向けのお知らせで分かるのは、当日の大まかなスケジュールだけ。
不安が強くて、先行きを色々気にして心配しちゃう子には「何をするか」だけでなく、具体的にどんなことが起こるのか説明する必要があります。
詳しい予定は、個別に先生に質問しました。
「お泊り保育」でやること&流れ(スケジュール)

息子の保育園の「お泊り保育」では、夕食作り・花火・スイカ割りが主なイベントでした。
全体の流れとスケジュールは以下の通りです。
●1日目
~17:00 通常保育
17:00頃 カレー作り
18:00頃 夕食(カレー)
19:00頃 花火大会
19:30頃 シャワー&着替え
20:00頃 絵本の読み聞かせ
20:30頃 就寝
●2日目
6:00頃 起床
6:15頃 ラジオ体操
6:30頃 スイカ割り
7:30頃 朝食
8:30頃 帰り支度
9:00頃 お迎え(休日保育の子はそのまま園に残る)
細かい内容は園によって違うと思いますが、このレベルで事前に予定が分かると、親側も子供の様子が想像できて安心に繋がります。
※聞かないと分からなかった予定(読み聞かせ等)もあります。想像できないことは、先生に直接聞きました。
いつもと違う「一大イベント」の説明どうする?
「お泊り保育」の準備は、運動会や遠足などの年間行事とは、レベル感が違いました。
本人にとって、夕方まで頑張れば家に帰れる・時間が来ればお母さんが迎えに来る・夜は好きな図鑑やYoutubeが観られる・お母さんと眠る…という、”いつもの安心材料”がありません。
この、いつもと違う「一大イベント」を迎えるにあたり、息子への説明タイミングが難しかったです。
「お泊り保育」の説明が早過ぎても、変に不安感を煽って、勝手に想像されて、「行きたくない!」という気持ちに繋がる恐れがあり。
また遅すぎても、色々と焦りが生じて、心配事が思い浮かぶ度にパニックに繋がる恐れがあり。
説明のタイミングや方法が1つ間違えば、不安な気持ちに刺激を与えてしまいます。
「お泊り保育」について、息子にいつ、どうやって説明するかが問題でした。
「心の準備」と「実際の準備」は切り分ける
そこで、「お泊り保育」の説明・準備は、「心の準備」と「実際の準備」に分けることにしました。
本人がゆっくり把握して、「イメージできれば安心もできる」という状態にしたいので、説明のタイミングも変えました。
心の準備・・・お泊り保育の「存在」を受け止める
・タイミング:2ヶ月前くらい
・内容:お泊り保育が「あること」を教える。
・目的:お泊り保育の存在を受け止めてもらう
・ゴール:「不安だけど行きたい」という気持ち
実際の準備1・・・お泊り保育で「やること」をイメージする
・タイミング:数週間前くらい
・内容:お泊り保育で「やること」を教える。
・目的:お泊り保育で何をやるのか理解する。
・ゴール:「不安だけど〇〇をやりたい」という気持ち
実際の準備2・・・お泊り保育の「持ち物」を教える&揃える
・タイミング:数日前~前日
・内容:お泊り保育に「必要なもの」を教える。
・目的:お泊り保育で使う物を把握する。
・ゴール:「これなら自分で〇〇できる」という気持ち
具体的に「やること」やどんなことが起こるのか教えて、お泊り保育への警戒心を解いていくことを目指すワケですが、タイミングを見計らって少しずつ説明を進めることになります。
心の準備対策1.「まだ先」「もうすぐ」を使い分ける
まずは、心の準備対策。
お泊り保育の存在を伝えると、不安の強い子は当然、「どこに泊まるの?」「寝る時どうするの?」「お母さんは?」と質問攻めが始まりました。
息子が「お泊り保育」の存在をまだ受け止め切れていない時は、「まだ先だから大丈夫だよ。」と軽く流すことに。
暫くすると、本人が先生や友達から何かを聞いて、お泊り保育で「楽しそうな何かをやるらしい」と少しずつ分かって来ると、「スイカ割りやるんだって」「スイカ割りってどうやるの?」と具体的な質問が増えました。
具体的に聞かれた時は、「もうすぐだね。スイカ割り楽しそう。羨ましいな~」という感じで答えることに。
息子は私に対する承認要求が強めで、私に羨ましがられると喜ぶ傾向があるので、「お泊り保育=楽しみ」という気持ちになるように、たくさん羨ましがりました。
こうして、息子の不安具合に合わせて「まだ先」と「もうすぐ」を使い分け、更に「もうすぐ」を使う時は羨ましい気持ちを強調しました。
心の準備対策2.「お泊り保育までに〇〇ができるように」と言わない
もしも今、できないことや苦手なことがあって「お泊まり保育までに〇〇ができるようになろう」と言われたら、どういう気持ちになりますか?
息子の場合は、「お泊り保育なんて無ければいいのに」「どうしてお泊り保育があるの?」という気持ちになると思います。
お泊り保育が「楽しみ」になって欲しい時に、親子して「お泊り保育までに〇〇ができるようになる!」なんて焦ったら、お泊り保育が1つの壁(ハードル)になって、気分が滅入ると思いました。
×「一人でベッドに行けるようになろう。」
×「言われなくても、歯磨きして顔を洗えないとダメだよ。」
×「夜のおねしょを治さなといけないよ。」
etc…
このタイミングで「お泊り保育までに(~が)できるようになろう」とは、絶対に言わないように気を付けました。
心の準備対策3.普段の「できた」をお泊り保育に関連付ける
その代わり、いつも通り過ごす中で、何かができるようになった時は、お泊り保育に関連付け。
普段の「できた!」を、お泊り保育に関連付けて、本人の自信に繋げます。
例えば、お風呂で髪を洗い流す時。
息子は、お湯が頭の上から顔に流れ落ちると嫌がりましたが、少し我慢ができた時は、

…という、いつもの「できた」→「褒める」に加えて、

「お泊り保育でも大丈夫」ということを意識させました。
不安だけど「お泊り保育」に行ってみたい、〇〇ができるようになったから「お泊り保育」でも大丈夫そう…という意識が芽生えた頃、いよいよもう少し踏み込んで、具体的な準備&対策を開始します!
心の準備対策4.お泊り保育の練習だと分からないように練習する
実際のところ、顔に僅かなお湯がかかっても大丈夫というレベルでは、お泊り保育のシャワータイムを乗り切れません。
先生が次々と園児の頭からジャージャー流す「シャワー」で、うろたえず躊躇せず泣かずに平然と!
みんなと列に並んで洗われるためには、もっとジャージャーと上からかける練習が必要でした。
お泊まり保育に向けて練習しつつ、本人には「お泊り保育のための練習だ」と分からないように、さり気なく練習を積むことに。

お泊り保育までに、頭上からシャワーが3秒間かかっても、自分で目をつぶり耳を抑え、顔をぬぐって目を開ける…ができるようにしました。
「心の準備」ができたら、本来の対策スタート!
こうして2ヶ月ほど「さり気ない準備」をしていると、息子の反応に変化が起こりました。
お泊り保育の話題が出ると、最初は「お泊り保育やだー」と言っていたのに、
「お泊り保育で、〇〇だったら、どうする?」
「お泊り保育、いつ?」
「お泊り保育で、寝る時、壁側かなぁ?」
など、”お泊り保育ありき”の心配をするようになったのです。
息子本人が、「お泊り保育」の存在を受け止めたんだなぁ~と実感。
ここからが本番、本来の「お泊り保育の準備対策」がスタートしました。
各イベント・持ち物・流れ…に分けて説明
※お泊まり保育に関わる持ち物のご準備は、お子様と一緒にお願いします。
「お泊まり保育のお知らせ」より
保育園から配られた手紙には、子供と一緒に持ち物の準備をするように書いてありました。
普段の保育園生活でも「自分のことは自分でやる」を目指してみんな頑張っていますが、お泊り保育は更なる成長が期待されるイベントでもあり…親もプレッシャーを感じます。
自分の持ち物は自分で管理する…は分かるけど、息子の場合は「持ち物の準備」以前に、理由や背景の説明も必要でした。
なぜそれを持って行くのか、いつ使うのか、使ったらどうするのか。
混乱を避けるため、これを一気に教えるわけにもいかず、
・お泊り保育でやること(各イベント)
・使うもの(持ち物)
・いつどこで使うか、使ったらどうするか(流れ)
に分けて、教えました。
未経験を「知ってる」にする!ジェスチャーでエア練習
1つ1つのイベントは、どんな行事なのか教えて、どんな様子なのか息子がイメージできることを目指います。
例えば「花火」は、実際の思い出を引き合いに説明し、写真や実物を見せてイメージ。
「スイカ割り」は未経験なので、ボールと玩具の刀を使って実演。
やり方だけでなく癇癪対応(情緒の安定対策)として、もしも割れると思っていたスイカが割れなくても、それはそれで楽しい場面だと分かるように演じました。
棒がスイカ(ボール)に当たらなくても悔しがる(渾身の)演技を見せて、息子を大笑いさせておきました。
こうして、ジェスチャーを駆使してエア練習(≒シミュレーション)することで、未経験でも「それ、知っている」と言える状態にしました。
お泊り保育では、「知ってる!」と思っていることを実際に皆とやるだけ、にしておくと(親も)安心です。
お泊り保育の「夜のオムツ」どうする?
夜におねしょをする子にとって、宿泊行事は一大事。お泊り保育に向けて、夜のオムツを外そうと、必死に頑張るご家庭も多いのではないでしょうか。
私は、オムツ外しは到底間に合わないと分かっていたので、担任の先生に「夜寝る時のオムツ」について確認しました。
- 夜は「オムツ」で全然OK
- 去年のお泊まり保育では、半分近く「オムツで寝る子」がいた
- 寝る時のオムツは、リュックに入れておけばOK
- シャワーの後、パジャマに着替える時に、夜のオムツを装着する
- 朝起きた時、濡れたオムツは担任が処理する
ということが分かりました!
夜オムツ・おねしょ対応は先生と連携する

お泊り保育で夜、オムツをはいても大丈夫なこと、おねしょをしても大丈夫なことをあえて先生の前で、息子に言いました。

と、先生からも息子に言ってくれました。
夜オムツとおねしょ対策は、先生と連携することでだいぶ解決しました。
夜オムツが安心材料に!”一人で寝られない”も「仕方がない」に
心配していた「夜オムツ&おねしょ」の件が、息子なりに解決したことで、「これなら夜、保育園で眠れる」という気持ちに繋がりました!
息子にとって「お母さんと一緒に寝られない」という最大の不安も、ある種の「諦め」に転じたようです。
お泊まり保育の過ごし方が色々イメージできたことで、少しずつ「不安だけど楽しみ」になってきている様子。
「お母さんと寝られない」という大問題でさえ、「仕方がない」という感情に変わっていました。
全体の流れ(スケジュール)は最後に説明!絵で視覚支援
こうして息子の不安を和らげ、いざ、お泊まり保育の全体スケジュールを説明したのは、もう前日。ギリギリのタイミングでした。

全体の流れ(スケジュール)を説明するために、お泊り保育でやることを絵に描きました。

息子が得意とする、視覚に訴えます。(視覚支援)
1つ1つのイベントがイメージできていて、大きな不安が解消しているタイミングだからこそ、全体の流れの説明がスムーズでした。
※これが出来ていないと、全体の流れを説明している途中で、「これって何?」「この時どうするの?」etc…と質問攻めが始まって、説明になりません。(息子の場合)
最終チェック!各イベントのイメージを固める
ここまで来れば、あとは一緒に最終チェック。
お泊り保育の各イベントについて、1つ1つ具体的な説明を混ぜながら、イメージを固めて行きました。
カレー作り・夕食

・夕方から、エプロンをしてみんなでカレーを作る。
・教室でカレーを食べる。
花火大会
・「花火」は手に持ってやる花火。
・お空にバーンってなる花火ではない。
シャワー&着替え

・プールバックに、パジャマとタオルとオムツを入れる。
・水着に着替える。ズボンだけ。
・プールじゃないから、水着の洋服(=ラッシュガード)と帽子はいらない。
・みんなで並んで、シャワーに出発。
・順番が来たら、先生にシャワーを上からかけてもらう。
・終わったら、タオルで体をふく。
・パジャマを着て、紙オムツをはく。
絵本の読み聞かせ・就寝
・寝る前は、先生が絵本を読んでくれる。
・就寝
起床・ラジオ体操・スイカ割り

・朝が来たら起きる。
・布団を片付けたら、ラジオ体操。
・園庭でスイカ割り。
朝食

・朝ごはんは、おにぎり。
・スイカ割りで使ったスイカが、デザートに出てくる。
帰り支度・お迎え

・朝ごはんが終わったら、帰る準備。
・お母さんがお迎えに来る。
最後に「お母さんが迎えに来る」絵があることで、安心した様子でした。
忘れ物防止策!持ち物は「使う場面」毎にチェック
当日の朝は、いよいよ持ち物チェック。必要なものを一緒にリュックに入れていきます。
前日にイメージ固めした「お泊まり保育の流れ」の絵に沿って、その時々で必要になるものを並べておきました。
※園が用意した(普通の)持ち物リストではなく、本人が把握した「やること順」を参考にして、必要になる順にリュックに入れていきます。
「使う場面」毎に、何が必要になるか想像します。
(全体の流れの絵を使って)「ここで何を使うか?」とクイズを出しながら、その場面で使う荷物を1つ1つ、リュックに入れていきました。
大きな不安から「ちょっと楽しみ」へ!対策の効果

お泊り保育の当時、息子は「ちょっと、楽しみ」と言いました。
私は当初、「やーだ!やーだ!」と癇癪を起こし、嫌がりながらお泊り保育に向かう息子を想像していたんです。
お泊り保育の当日は、行き渋りされた時に、いつもの名ゼリフ「夕方に迎えに行くから、大丈夫だよ」が言えないので、何て応えれば良いのだろうかと、悩んでいたんです。
それなのに、「ちょっと楽しみ」と言ったんです。
毎日毎日、保育園に行くのを嫌がり、いつも何とか言い聞かせて連れて行っている息子が。
だから、息子のこの「ちょっと楽しみ」発言にとても驚き、涙をこらえるのに必死でした。
「お泊り保育」に向けて、すごく考えて準備&対策して大変だったけど、努力が報われた気がしました。
不安が強い子が「お泊り保育」に参加!

保育園に到着して、車から降りる時、息子は「でも、ちょっとは嫌なんだよ。」と言いました。
だけど、この時はもう、息子の気持ちがよく分かりました。

色々な気持ちが渦巻いて、楽しみだけど複雑な気持ちなんだろうな、とすぐ分かりました。

私が代弁してみた複雑な気持ちは当たったようで、息子は「お母さんは分かってくれている」という表情で深いため息をついていました。(緊張を抜く感じ?)
いろいろな気持ちが混ざる複雑な気持ちで、息子は「お泊り保育」に参加しました!
お迎えに行かない日、息子がいない夜はとても不思議な感覚でしたが、当日の私は思いのほか、不安よりも「きっと大丈夫」という気持ちでした。
「お泊り保育」の続編では、「クラス皆のおねしょ事情」「食物アレルギー対応」「お薬どうする?」について、まとめました。